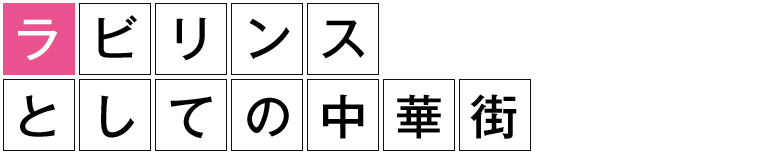関羽が読んでいるのは詩か簿記か。
想像をかきたてられる関羽像を買い求めて歩く大人の休日。

中華街は飲食の街であると同時に中華雑貨の街だ。美味と珍奇が並んでいる。ふらりと入った雑貨店で、不思議な関羽の像を見つけた。関羽といえば、三国志の英雄。長い槍のようなもの(正しくは青龍偃月刀=せいりゅうえんげつとう、というらしい)を持っているのが大半なのだが、この関羽は座って本を読んでいる。老眼らしくその本をかなり目から離しているのがどこかおかしい。店員の中国人女性に聞くと、関羽は武将というだけでなく、詩をよくした人よ、というので、あるいは自作の詩か、荊軻や屈原の詩でも読んでいるのかもしれない。また一説によれば、関羽は簿記を発明した人とも伝えられているので、もしや武具や馬の数を記した簿記でも調べているのだろうか。簿記という日本語は、明治期に英語のbookkeepingの音から来たものといわれ、近代中国にもそのまま伝わり簿記と表記されるそうだが、その中国を代表するような関羽がまさにbookkeepingしている姿はなにやら二重におかしい。ともあれ、その関羽に見入っていたら店員の女性に、あなた相当関羽が好きなのね、半額にしてあげると、いわれたのでとうとう買ってしまった。関羽が何を読んでいるのかいまだにわからないが、机上にあって本を読む老将の姿を見ているのは、あれこれ想像をかきたてられ楽しいものだ。中華街にはこんな出会いもあるのである。

人を迷わせる中華街という街の不思議。
それは斜めに区切られた土地柄のせいか、それとも欲望のせいか。

横浜中華街に足を踏み入れると、なぜか方向感覚がずれてしまう。
そんな経験を持つ人が多いのは、なぜだろうか。グーグルなどで地図を見るとわかるのだが、周囲の道路が港に面して並行に走っているのに対して、横浜中華街だけは斜めになっているのだ。だから、碁盤の目のようになっている周囲の道路から中華街に足を踏み入れると、とたんに斜めの道路に入ってしまう。本人はまっすぐ入ったつもりなのに、街が斜めになっているため、感覚がずれてしまうのである。くわえて、中華街の建物の間から見える外のビルが斜めに見えるため、心理的にはよけい混乱しやすい。これが中華街で方向感覚がずれる要因なのだ。そもそも中華街の土地は、開港以前は横浜新田と呼ばれる耕地だったという。耕地で畑の畝(うね)を作る場合、日当たりがよくなるように南北に走らせるのが常識だが、その意味でも横浜新田は理に叶っていた。つまり、中華街は斜めではあるが、東西南北にそろっているのである。そうわかってしまえば、この街のラビリンスぶりはおそれるに足りない。空を見上げて日の昇る方向や沈む方向を見れば東西はわかるし、スマホのコンパスを確かめればよい。それでも迷うとすれば、それはあまりに多くの店、多くの料理、多くの匂いに、あなたの欲望が迷っているからである!

迷いながらも路地へ。裏道へ。
つい奥まった場所へと誘われてしまうのは、なにゆえだろうか。

日本最大であるばかりか東アジアでも最大規模といわれる横浜中華街。およそ500メートル四方の中に600店を超える店がひしめきあっているという。だが、いうまでもないが堂々たる大店が立ち並ぶメインストリートだけが中華街ではない。大通りから一歩離れた裏道や抜け道、路地裏などにひっそりたたずむ店も中華街そのものなのである。大店はたしかにわかりやすい場所にあるし、安心感もあるだろう。しかし、中華街というラビリンスのなかでは、大店とて色彩のひとつに過ぎない。ゆたかな色彩は、裏道や路地裏や人通りのはずれた場所のそこここに鮮やかに点在しているのだ。あえて店名を出すことはしないが、粥の名店ならばここ、刀削麺(とうしょうめん)ならここ、小籠包ならここ、と衆目の一致する店はたいていは路地裏である。あるいは大通りからはずれた場所である。
ラビリンスとは迷路をいう。ギリシャ神話におけるミノタウロスを閉じ込めた迷宮がラビリンスの語源になっているというが、そのミノタウロスとはそもそも食に貪欲で知られた怪物であった。そうしてみると、われわれが中華街を現代のラビリンスと感じ、知られざる美食を求めて奥へ、奥へとさまようのもまことにふさわしい話ではないか。大いに迷うべし。そして食すべし。